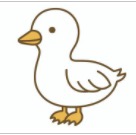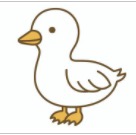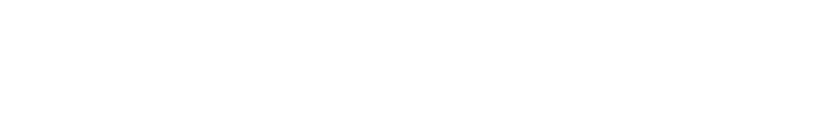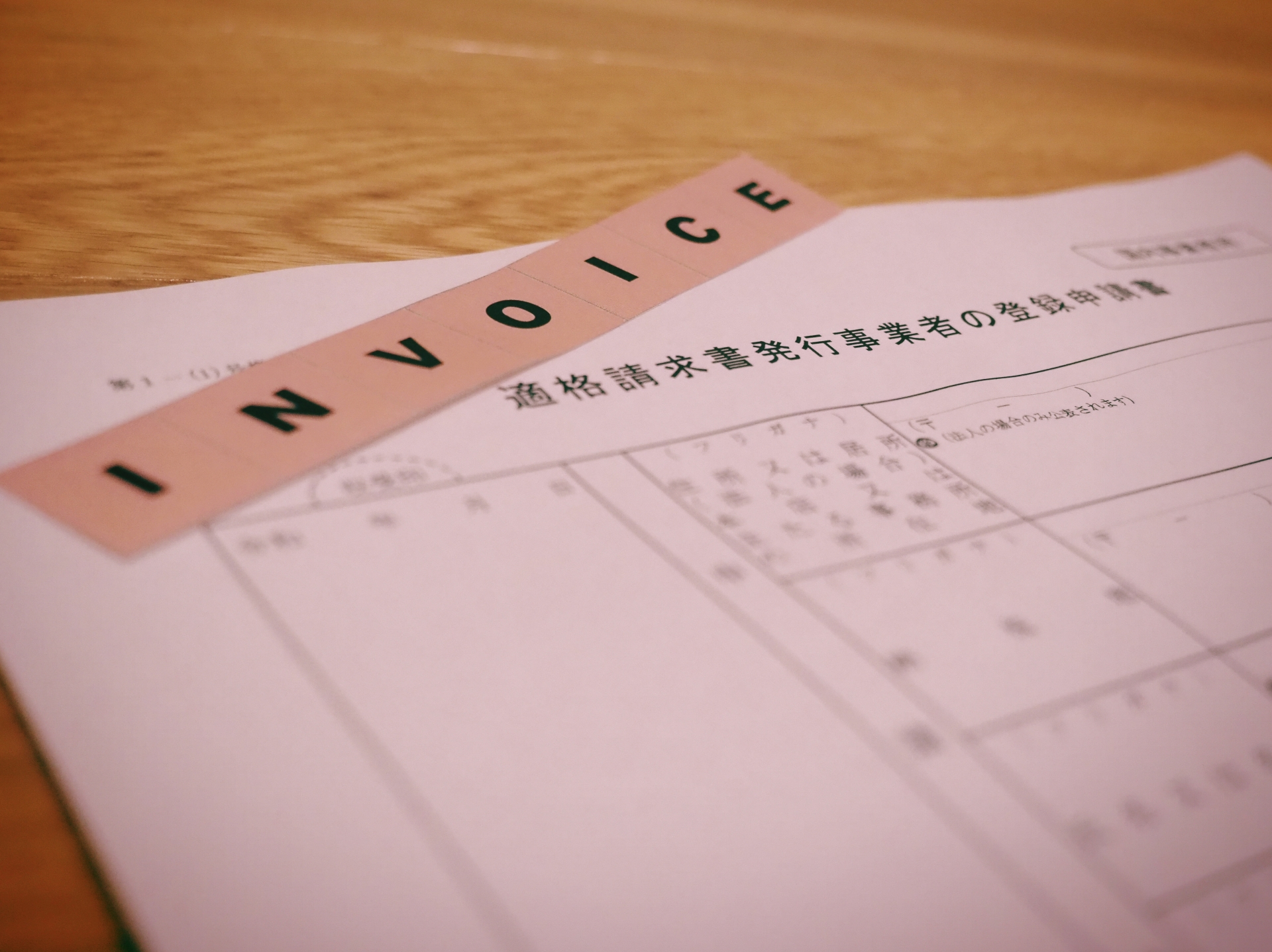去年から事業者の間でチラホラ話題になっている「インボイス制度」をご存知でしょうか。

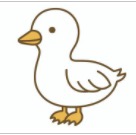
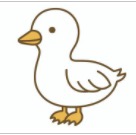

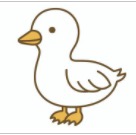
3つの動画を見れば難解な「インボイス制度の実態」を理解できる!
どんぶり勘定事務所の税理士 神田知宜氏の説明がわかりやすい!
インボイス制度はまず小規模な免税事業者(自営業・フリーランス)を着々と滅ぼし、その後にサラリーマン、日本国民全体に大損害を与える制度となっているようです。
こちらの動画をご覧ください。
インボイス制度を一言で言えば「登録番号のある課税事業者同士の取引でのみ消費税控除を与える」というもの。
インボイス制度は消費税についてだけの話であり、その他の税は関係ありません。
メリット
- 税務調査がしやすくなり、税金のとりこぼしを防ぐ(税収アップ)
- 消費税を15%・20%へ上げるための地盤づくり
- インボイス制度に関わっている役人が出世できる
- 新たな天下り先の創出

デメリット
- 増税による経営悪化
- 事務コストの増加(処理が煩雑になる)
- 事業主への負担が価格に転嫁され値上げ(物価上昇)
- 倒産・廃業が増える、景気の悪化
- 制度が理解できずトラブル続出
特に影響を受けるのは主に免税事業者が多い業界や仕事。
- 飲食業界(個人経営の居酒屋や定食屋・カフェ)
- スポーツ業界(スポーツ選手)
- 音楽業界(個人の音楽家や演奏家)
- 芸能業界(俳優やアイドル)
- 漫画・アニメ業界(漫画家やイラストレーター・声優)
- 出版・デザイン業界(デザイナーやライターやカメラマン)
- IT業界(エンジニアやWEBデザイナー)
- 教育業界(コンサルタントや個人教師)
- 運送業界(個人タクシーや個人運送業・ウーバー配達員)
- その他法人から仕事を貰う全ての事業
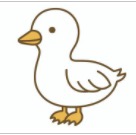
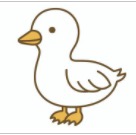
知らない人が多すぎるので何度でも言うぞ。
インボイスが始まったら「電力会社の消費税納税負担が580億円増えるため、その補填のためこっそり電気料金を値上げ」しようとしてる件。自分は無関係だと思い込もうが無駄、”インボイスは国民全員の問題”なんだよ!抵抗して廃止させよう💢 #STOPインボイス pic.twitter.com/FTb6FEcqSH— 桃太郎+ (@momotro018) April 6, 2023
「まぁサラリーマンの俺らにはカンケーねーな」と思うなかれ、日頃のストレス解消に行く飲み屋やランチが安くて美味い定食屋など、その多くは個人経営です。
ウーバーやタクシーだって個人で頑張っている所も多いですし、密かに応援している駆け出しのアーティストやスポーツ選手も辛い思いをすることになります。
大量の免税事業者に発注して仕事を回している中小企業もかなり負担が増してしまいます。
経営圧迫分を商品価格に転嫁せざる得なくなれば、回り回って(個人のサービスを利用する)サラリーマンにも被害甚大です。
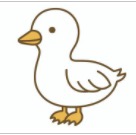


さらに、サラリーマンの中には「いつかは独立起業して自分の事業を〜」と夢見ている人もいるでしょう。
これも「消費税押し付け合い制度」で排除されないために最初から登録者(課税事業者)になっていないと明らかに不利であり、独立起業のハードルが高くなってしまいます。
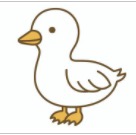

国民を洗脳し植え付けた消費税の誤解と益税論
「どうするインボイス制度」事業主の8割が総スカンで制度崩壊の足音迫る!?
こちらの記事では下記のように書いてあります。
消費税のインボイス制度は、消費税の納税義務を負う事業者が税額を計算する際に問題となる制度です。
少なからぬ人が誤解していますが、消費税は、「事業者」が納税義務を負う税金です。
事業者が、商品・サービスの価格の10%または8%(軽減税率)の額について納税する義務を負っています。一般消費者は納税義務を負っておらず、ただ、事業者が商品・サービスの価格に消費税相当額を上乗せすることが認められているだけです。
私たちが日ごろ「消費税を払っている」と思い込んでいるのは、正しくは、事業者が納税義務を負っている消費税の額を転嫁されているにすぎません。
本来、消費税は事業者が負担するものであり消費者が負担するものではない。
つまりお店でよくみる「商品価格+税」は事業者が払う消費税を転嫁した額を記載しているだけなのですが、それを私たちはいつの間にか「消費者が払う税金」と誤解して受け入れているという現状があります。
故にインボイス制度に賛成する人達からは「そもそも免税事業者は貰った消費税分を自分の懐に入れて得してるだろ!それができなくなっただけじゃねぇか!」という主張が見受けられます。
これを「益税論」といい、益税論は「消費税は預かり金である」という前提で展開されています。(消費者から預かった税金)

しかし消費税が預り金かどうかというのは1990年に東京地裁と大阪地裁の裁判で「預かり金ではない」という判決が出ています。
判決は「消費者は、消費税の実質的負担者ではあるが、消費税の納税義務者であるとは到底いえない」「(消費税の)徴収義務者が事業者であるとは解されない。
したがって、消費者が事業者に対して支払う消費税分はあくまで商品や役務の提供に対する対価の一部としての性格しか有しないから、事業者が、当該消費税分につき過不足なく国庫に納付する義務を、消費者との関係で負うものではない」。
つまり、消費税は物価の一部であり、「預り金」ではないと判決ではっきり言っています。この判決は控訴しなかったことで確定しました。こう主張したのは、ほかでもない税務署側、国側なのです。
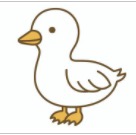
こちらの動画をご覧ください。
そのため「免税事業者は消費税をくすねて得している」という益税論は誤解である上に、言葉通り「消費税相当分をくすねている」のであればそれは横領(犯罪行為)ですし、認められる訳がありません。
認められているのは「売り上げの低い小規模事業者の消費税納税にかかるコストや労力を配慮して免税措置を講ずる」という方針から「免税事業者」という括りが生まれたからです。
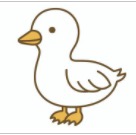
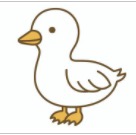
「消費税は安定財源」とか抜かす前に、そもそも『”消費税”は消費者から預かって事業者が納める益税だという説明、および、社会保障に使うというのは財務省と政府による大ウソでした!嘘で国民を長年騙してきてスミマセンでした』って謝罪するのが先だろうが💢#消費税の真実pic.twitter.com/u0dR1wESqT pic.twitter.com/g0N3syErkz
— 桃太郎+ (@momotro018) April 11, 2023
インボイス制度は「免税事業者を窮地に立たせ消費税を巻き上げるための制度」になっていながらも免税事業者の制度は残し続けるという矛盾を孕みながら突き進んでいます。

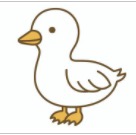
ちなみに消費税法の条文には「消費者」という言葉は出てきません。
(課税の対象)
第四条 国内において事業者が行つた資産の譲渡等(特定資産の譲渡等に該当するものを除く。第三項において同じ。)及び特定仕入れ(事業として他の者から受けた特定資産の譲渡等をいう。以下この章において同じ。)には、この法律により、消費税を課する。(納税義務者)
第五条 事業者は、国内において行つた課税資産の譲渡等(特定資産の譲渡等に該当するものを除く。第三十条第二項及び第三十二条を除き、以下同じ。)及び特定課税仕入れ(課税仕入れのうち特定仕入れに該当するものをいう。以下同じ。)につき、この法律により、消費税を納める義務がある。
全て「事業者の話」であり、「消費者にどうこうというような話」はどこにも出てきません。

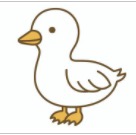
死ぬまで同じ立場でいられると考えるエリートのルサンチマン
また、稼ぎの良い人は「俺らは満額税金払ってる!なのにこんなしょーもねー奴らは堂々と税金免除されて、俺らの払った税金で公共サービスをのうのうと受けるのか?許せん!」という視点から腹を立てます。
これを「エリートのルサンチマン」や「逆ルサンチマン」というそうです。
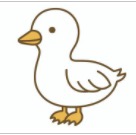
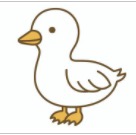


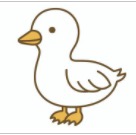
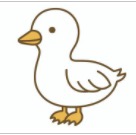

インボイス制度の抜け道とは制度自体を拒否すること
最後にインボイス制度の対策ですが、こちらの動画をご覧ください。
ウソに注意
- 「もう決まったことだし諦めるしかない」はウソ(登録者が少なければ導入されない可能性)
- 「法律を変えるのはハードルが高い」はウソ
現状、免税事業者の登録割合は20%くらいとのことです。

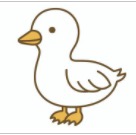
ボイコット作戦
- ギリギリまで登録しない(導入させないためにギリギリまでチキンレースを講じる)
- すでに登録してしまった人は取り下げる
早く登録しようが遅く登録しようが(予定通り導入されるなら)スタートは10月1日なので、焦らないビビらないことが大切とのこと。

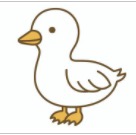
2023/8/22追記「インボイス取り下げ激増中です(全国商工団体連合会)」
世界情勢を解説で人気の及川幸久さんの動画では「インボイスの取り下げが激増している理由と、インボイス登録が不要である理由、LLPの勧め」など有益な情報を話してくれています。
5つの動画+αとして知っておいて損はない内容でした。
私もLLPは知らなかったので見て良かったですね。
さいごに
動画を繰り返しみて理解を深めると迷わない
特に最後の動画では「個人事業主が使える裏技」「(登録について)取引先への答え方」も紹介されているので、知っておいて損はありません。